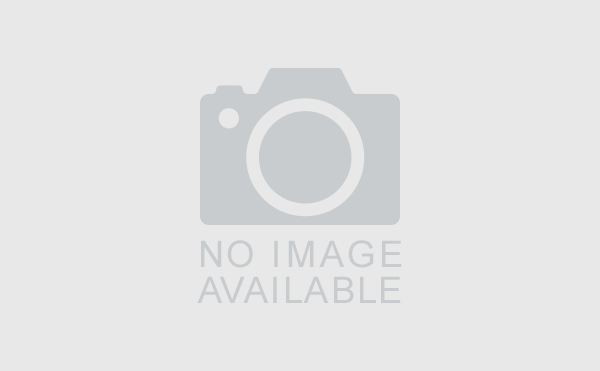【休眠預金】対馬市のユースアンサンブルから広がる音楽の輪(長崎県対馬市 Vol.2)
NPO法人長崎OMURA室内合奏団 対馬ほほえみ会第2回インタビュー
長崎県対馬市の小中高生による「対馬ユースウインドアンサンブル~BestSmile~」を指導するNPO法人長崎OMURA室内合奏団と、アンサンブルメンバーの移動支援に取り組む対馬ほほえみ会。アンサンブルに寄せる想いや移動支援の仕組みなどを伺った第1回のインタビューから約4カ月が経過し、新たな変化が生まれたようです。それはどんな変化なのか、そして、持続可能な体制の構築に向けてどう考えているのか。アンサンブルと移動支援の立ち上げにかかわったNPO法人長崎OMURA室内合奏団の亀子政孝さん(以下、亀子)と、対馬ほほえみ会事務局長の安田壽和さん(以下、安田)に話を聞きました。
音楽が生んだ情熱と裾野を広げる新たな取り組み
――第1回のインタビューから約4カ月が過ぎました。どんな変化がありましたか。
亀子: 子どもたちの技術が格段に向上しました。中高で部活動していない子どもたちの方が多いのですが、練習に行くたびに上達を感じることができます。情熱が高まっているのも感じられます。あるコンサートで不手際があり、前日のリハーサルで楽譜を渡すというトラブルがありました。当然、リハーサルの時間だけでは曲は完成しませんでした。しかし、子どもたち自宅に帰って練習し、リハーサルの時とは全く違った完成度の曲を本番で演奏してくれました。これは子どもたちが吹奏楽を好きになり、情熱を持って取り組んでいる結果だと思います。実際、ある子は「学校に行くよりユースの方が楽しい」と言ってくれました。うれしかったですね。正直に言うと、毎回泣きそうになるくらい感動しています。私の方が「ありがとう」と言いたくなるような気持ちでいっぱいです。
安田:2024年の11月時点ではメンバーが中学1年生から高校3年生までの11人でしたが、25年3月末時点で小学6年生から高校3年生までの15人に増えました。少しずつ認知度が広がり、活動が地域に浸透してきていると感じています。市長への要望活動を行い、対馬市公会堂という文化ホールから閉園していた保育園へと練習場所も変わりました。これまで社協から持ち運んでいた楽器を保管できるようになり、よりスムーズに活動できるようになりました。
――3~10歳を対象にした「キッズサウンドクラブ」も立ち上げたそうですね。
安田:吹奏楽はある程度の技術や基礎が必要になるため、小さな子どもたちにとっては難しい部分があります。そこで、まずは音楽に親しんでもらい、興味を持ってもらおうと「キッズサウンドクラブ」を立ち上げ、打楽器を楽しんでもらう場を作ることにしました。募集を始めたばかりで集まるかまだ分かりませんが、より多くの子どもたちが音楽に興味を持ち、ユースクラブへの参加へとつながっていくことを期待しています。指導はドラムの演奏経験がある一般の方と、保育所の先生をされていた方が担ってくれます。お願いしたところ、快諾してくれました。OMURA室内合奏団からも打楽器の奏者が指導に来てくれることになっています。
亀子: とても素晴らしい取り組みですよね。音楽を好きになる子どもが増え、将来的にユースクラブへとつながっていけば意義のあることですし、たとえユースに入らなかったとしても音楽を楽しめる人が増えること自体が、地域の文化にとって大きな財産になります。すぐに成果が出るものではありませんが、活動を長く続けていくことで豊玉地区にとって音楽が身近な存在となってくれたらと願っています。

=新たな練習場所となった保育園で子どもたちはレベルアップに励む=
持続可能性の鍵は指導者確保と資金調達
――移動支援に関して新たな課題は見えてきましたか。
安田:送迎を担当する運転手が固定化され、特定のメンバーに負担が集中してきたことです。安全面を考慮し、現在は研修を受けた10人が運転できるようになっていますが、それぞれに仕事があります。送迎には片道1時間ほどかかるため、仕事の合間を縫って送迎のスケジュールを調整するのが難しい状況です。その結果、主に役員が担当している形になっています。今後はより柔軟な運営体制を模索していく必要があると思いますし、協力してくれるようメンバーに引き続きお願いしていこうと考えています。
――現在はクラブ費として月1000円、移動支援の料金として最大1000円を徴収しています。約1年後の2026年2月に休眠預金事業が終わった後も、これまで通りの活動を継続する上での資金的な問題はありますか。
安田:NPO法人化することで活動を継続していけたらと考えています。個人や任意団体のままでは申請できない助成金や補助金でも、法人格を持つことで申請が可能になるなど運営資金を確保しやすくなります。ただ、休眠預金事業の終了後、OMURA室内合奏団の方々が定期的に指導する体制を続けることは難しいかもしれないので、その可能性も踏まえて対馬市内で自走できる体制を整えていく必要があると考えています。とは言え、OMURA室内合奏団の方々は、休眠預金事業が終了しても学校の演奏会などで対馬を訪れる機会があるかもしれません。その際に短時間でも指導をお願いするような方法を取り、完全に関係がなくならないよう適切な形でつながっていければと考えています。
――持続可能な体制を構築する上で、子どもたちに教える指導者の確保と育成も重要ですね。
亀子: そこが最大の課題だと思います。現在は、現地の学校の先生方が指導を担当してくださっていますが、先生方は異動がありますし、特定の個人の努力や犠牲に依存している状況では、長期的に継続するのは難しいと考えています。今後については、現地の先生方としっかりと相談しながら、どのようにバトンを渡していくのかを考える必要があります。理想としては、このユースで育った子どもたちが、将来対馬に戻ってきて指導者となり、ユースの活動を引き継いでいくことです。しかし、それには長い時間がかかる上、そうならないかもしれないので、いずれにしても指導者の確保は重要課題です。個人的には可能な限りお手伝いを続けたいと考えていますが、私たちが公式に関わるのは2026年2月までです。残された期間の中で課題をもう少し掘り下げ、具体的な解決策を見つけていきたいと思っています。
安田: これまでも「指導をお願いできないか」という依頼は続けていますが、承諾が得られていない状況です。ピアノの経験はあっても吹奏楽の楽器に関する経験がないというケースも多いです。また、指導することに対してハードルを感じている方も少なくありません。「教えたい」という気持ちはあっても、専門的な知識や技術がないためになかなか指導に踏み出せないという現状があります。持続可能性を見据えて資金と指導者の問題は常に念頭に置いています。

=プロジェクトを支える室内合奏団とほほえみ会のメンバー=
対馬に愛されるアンサンブルを未来へ
――どれくらいの頻度でイベントに出演しているのですか。
亀子:新しい練習会場でお披露目コンサートを開催しまし、その前は11月の芸能発表会に出演しました。さらに雲仙市の団体と共演したイベントもありました。振り返ると月に1回程度の頻度でイベントに出演していると思います。これだけ頻繁に出演できているのは、関係者の皆さんが尽力し、演奏の機会を積極的に見つけてくれているおかげです。
安田:演奏は指導者の先生方が直接手配されることもあれば、私たちが情報を得て「この発表会に参加できませんか?」と提案し、申し込むケースもあります。発表の場があることで「もっと上手になりたい」という気持ちが強くなり、モチベーションが高まっているので、さまざまな形で演奏の場を確保しています。練習を重ねるごとに子どもたちがどんどん上達していく姿を見て「次の発表をする機会をなんとか見つけてあげなければ」という気持ちになっています。
――残りの期間にかける想いをお聞かせください。
安田:対馬の皆さんにもっと吹奏楽に興味を持ってもらい、参加者が増えてくれたら嬉しいと思っています。メンバー数は20名ほどまで拡大できるよう、体験会の開催などにも努力していこうと考えています。また、どんな場所でも演奏会が開けるような体制を整えていくことも目標の一つです。
亀子:ユースが地域の人々に愛され、対馬市のみんなにとっての「宝物」になってほしいと思っています。そして、地域全体で育ててもらえるような団体になれば最高ですね。対馬市は、子どもの数が減少して学校も少ない上、距離が遠いために集まりにくいという課題があります。そうした厳しい状況の中でも、少しずつ努力を重ねることで続けられています。この先も地域の皆さんに愛される存在として、このアンサンブルが続いていってほしいと心から願っています。子どもたちは間違いなく音楽が好きです。好きに上限はないので、もっともっと好きになってほしいと思っています。そのために僕ら指導者は全力で演奏し、子どもたちに「かっこいい」「自分もこうなりたい」と思ってもらえるような姿を見せたいと思っています。ほほえみ会が対馬の皆さんにとっても「いいな」と思える存在になれるよう、これからも尽力していきたいです。

=対馬市ふれあいコンサートで演奏。発表の機会が確保され着実に経験を積んでいる=
投稿者プロフィール
最新の投稿
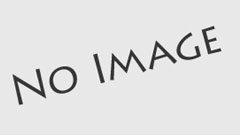 お知らせ2025.12.27年末年始のご案内
お知らせ2025.12.27年末年始のご案内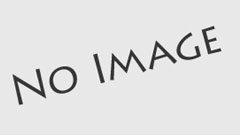 お知らせ2025.11.29【開催案内】休眠預金活用事業2022年度通常枠『こどもの成果発表会』開催!!
お知らせ2025.11.29【開催案内】休眠預金活用事業2022年度通常枠『こどもの成果発表会』開催!!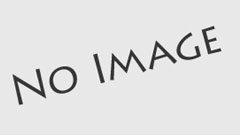 お知らせ2025.05.27【休眠預金】『子どもの移動と体験を考える地域円卓会議in長崎』開催のご案内
お知らせ2025.05.27【休眠預金】『子どもの移動と体験を考える地域円卓会議in長崎』開催のご案内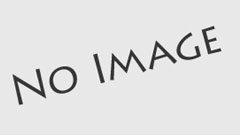 お知らせ2025.04.23【休眠預金】対馬市のユースアンサンブルから広がる音楽の輪(長崎県対馬市 Vol.2)
お知らせ2025.04.23【休眠預金】対馬市のユースアンサンブルから広がる音楽の輪(長崎県対馬市 Vol.2)