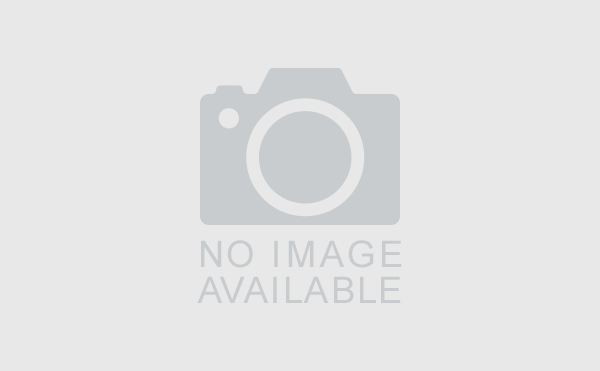【休眠預金】眠る楽器で奏でる音色、音楽が未来を照らす島へ(長崎県対馬市)
未来基金ながさきは、休眠預金等活用事業(2022年度通常枠)の助成先として一般社団法人高島活性化コンベンション協会ESPO(佐世保市高島町)と認定特定非営利活動法人長崎OMURA室内合奏団対馬ほほえみ会(対馬市)、うんぜん部活動移動支援実証実験運営協議会(雲仙市)の3団体を採択した。3団体は今後、休眠預金を活用して「地域共生社会で子ども達の故郷を無くさない」をテーマに「文化」と「交通」の2分野における課題解決に取り組む。その中でどんな困難に直面し、乗り越え、どんな成果を生んだのか―。それぞれの取り組みをシリーズで届ける。
眠る楽器で奏でる音色、音楽が未来を照らす島へ
人口減少や少子化により、音楽に触れる機会が失われつつある九州最北端の離島、対馬市。中学校11校、高校3校のうち吹奏楽部があるのはわずか2校という現状の中、大村市のプロオーケストラ「長崎OMURA室内合奏団」と対馬市の中圏域で移動支援を行う「対馬ほほえみ会」が手を組み、音楽教育と移動支援を通じて対馬市の未来を築くプロジェクトを始めた。廃校に眠る楽器を活用し、楽器に触れる機会を子どもたちに提供するプロジェクトに込めた想いや描いている未来について、同合奏団事務局長の藤﨑澄雄さんと対馬ほほえみ会副会長の原田順子さんに話を聞いた。
2つの団体が描く新たな未来、音楽が遠ざかっていく島での挑戦
中学校や高校で吹奏楽部が活動するのは、南圏域にある厳原地区のわずか2校。中圏域の豊玉高校では2014(平成26)年に、北圏域の上対馬高校の吹奏学部は24年の夏に廃部となった。南・中圏域で暮らす子どもたちが楽器に触れるには、厳原地区に通う、もしくは住むしかなくなっていった。
「寂しかったし、残念でたまりませんでした」。かつて厳原地区の高校に通い、吹奏学部に所属していた原田さんは言う。「子どもが家で楽器を練習している姿を見ると、家族全員が楽しい気分になれる。音楽は子どもたちだけでなく、保護者や家族にも喜びをもたらすのに」。音楽の力を信じているからこそ、現状への歯がゆい想いが募っていた。
プロジェクトの話が持ち上がったのは、21年ごろ。未来基金ながさきの呼びかけにコンサートや青少年育成などを約20年間続けている長崎OMURA室内合奏団が応じた。
そして、高齢者の通院や買い物などの移動支援を行っていた対馬ほほ笑み会にも声がかかった。原田さんは「話をいただき、すぐに飛びついた」と即決した。
藤﨑さんは「合奏団が拠点を置く大村市は、珍しく人口が増えている。そのため、廃校や廃部の話を聞くことはほとんどない。だからこそ対馬の現状に大変ショックを受けたし、少しでも役に立てればと思い、このプロジェクトに関わることを決めた」と振り返る
こうして、遠ざかっていた音楽環境を引き戻す歯車が回り始めた。

=長崎OMURA室内奏団事務局長の藤﨑さん(左)と対馬ほほえみ会副会長の原田さん=
指導者と送迎の課題を解決、よみがえる吹奏楽の音色
プロジェクトを進める上で、2つの課題が浮かび上がった。一つは現地の指導者をどう確保するか。もう一つは子どもたちの送迎に関する課題だ。
合奏団のメンバーが指導する方針は決まっていた。しかし、毎週通うのはスケジュール的、資金的に非現実的な上、合奏団に依存し過ぎては持続可能な体制は築けない。そのため、藤﨑さんは「現地の吹奏楽経験者と連携し、子どもたちと指導者の双方を育成しようと考えた」と語る。
対馬市にも吹奏楽経験者はいた。だが、子どもたちの指導を引き受けてもらうことはできなかった。仕事と指導を両立できるのか。そんな不安が、引き受けてもらえない背景にあった。指導者を確保しなければプロジェクトが進まない。そう悩んでいた時、光明が差した。2024年春の異動で、吹奏楽経験者の教員が中圏域に赴任。指導の役目を快諾してくれた。藤﨑さんは「優秀で指導力のある先生が3人も来られたのは幸運でした」と感謝する。
ほほ笑み会は、保険に加入したり運転に関する講習を受けたり一定の安全対策を講じた上で、高齢者の移動支援を会員の自家用車で行っていた。ただ、「もしものことがあったら」と、自家用車の使用に否定的な意見は常に挙がっていた。今回のプロジェクトでもそうだった。そこで、軽自動車の新車4台を購入。原田さんは「公用車を導入したことで、不安が解消されて安心して活動できるようになった。運転手が4人ほど増えた」と話す。
こうして指導者と送迎に使用する車の問題を解決した。並行して、合奏団によるコンサートや楽器体験会を中圏域の豊玉町にある対馬市公会堂で開催するなどして、子どもたちの募集にも取り組んだ。そして24年9月7日、新車のお披露目会を兼ねた移動支援出発式を実施。部員8人が集まり、「対馬ユースウインドアンサンブル~BestSmile~」が発足した。この日、第1回目の練習が行われた。初心者もいる中、約3時間後には「カエルのうた」を合奏することができた。吹奏楽の響きが消えた豊玉町を、初々しい希望の音色が覆った。

=指導を引き受けた北森先生=
資源を最大限に活用、子どもたちを支える廃校の楽器
プロジェクトでは、廃校となった学校に眠る楽器を活用している。これらの楽器は市や県の教育委員会が所有しており、現在は合奏団が許可を得て借り受けた状態だ。しかし、その多くは長年使用されておらず、傷みが目立っていた。そこで、合奏団は専門業者に修理を依頼し、全ての楽器を点検・メンテナンスした上で子どもたちに貸し出している。
「新品を購入した方が早いのですが、現在価格が高騰しており、例えば30人分を揃えるとなると最低でも1500万円ほどかかります」と藤﨑さん。限られた資源を最大限活用するため、この方法を選択したという。
練習は週に1回だが、子どもたちは楽器を自宅に持ち帰り、日々練習に励んでいる。公共物である楽器は通常持ち出しが禁止されるが、「家庭での練習がこのプロジェクトの鍵を握っている」と藤﨑さんは語る。廃校の楽器は再び音を奏で、未来を育む大切な道具となっている。

=廃校の楽器を活用したことについて語る藤﨑さん=
大役担うほほ笑み会、子どもを支える送迎支援
子どもの送迎は、ほほ笑み会のメンバーが担当する。出欠確認や送迎の時間、往復の利用か片道の利用かをLINEで確認している。原田さんは「中高生の保護者はLINEをよく使う世代でスムーズにやり取りできている」と話す。
利用料は片道20㌔未満は100円からで、最大1000円。安価な料金も検討したが、今後の活動に必要な経費や持続可能性などを踏まえて設定した。対馬ユースウインドアンサンブルのメンバーは11人(24年11月時点)。練習会場の豊玉町まで1時間から1時間半かかる厳原地区の中学3年生2人は「とっても助かっている」と感謝する。
藤﨑さんもほほえみ会会員の努力に敬意を表した上で、この努力をさらに知ってもらえるよう、こう願う。「気持ちは若くても高齢の方々が送迎を担っている。そうした方々が、地元のみならず他の地区の子どもを送迎することは、普通では考えられないこと。大変な役割を担ってくれている。保護者の方々には、その苦労を理解してほしい」。

=原田さんは自身も楽しみながらアンサンブルの活動を支える=
音楽の力で喜びつなぐ、結成2カ月で初舞台へ
対馬ユースウインドアンサンブルの練習は週末の1回。教員3人が中学1年生から高校2年生までの11人(24年11月時点))を指導している。中学3年の女性メンバーは「先生がいっぱいいて細かいところを教えてくれる。レベルが上がったと思う。入ってよかった」と充実した様子だ。
合奏団は月に1、2回指導にあたる。別の中学3年生の女性メンバーは「レベルに合わせて教えてくれる。成長しているのが分かる」とプロの指導に感謝。「音楽を通して喜びを共有できる。入ってよかった」と話す。
対馬ユースウインドアンサンブルは結成から約2か月後の24年11月、豊玉町芸能発表会で初ステージに立った。披露したのはカントリーロード。豊かな自然に囲まれ、穏やかな時間が流れる豊玉町にぴったりな曲を堂々と奏でた。中学3年生の女性メンバーは「緊張したが楽しかった」と笑顔を見せた。
プロジェクト立ち上げ当初は「こんなところでやっても子どもが少ないから無理だ」「楽器を知らない子ばかりではうまくいかない」といった否定的な意見が挙がっていた。それだけに、会場で初舞台を見届けた原田さんは「涙が出そうだった」と話す。
アンサンブルの演奏を初めて聴いた藤﨑さんは自身の経験から「このプロジェクトに関わる人々には熱意がある。成功する」と力強く語る。藤﨑さんは大村市で市民ミュージカルの発足に関わり、その活動は20年以上続いている。ミュージカルは多くの参加者の人生を豊かにし、中には宝塚歌劇団や東宝に進んだ人もいる。こうした経験から「1人でも2人でも集まれば、継続することで必ず上達する」と断言し、アンサンブルが対馬で新たな音楽文化の礎を築くことを期待している。

=初舞台で堂々と演奏したアンサンブルのメンバー=
奏で続けるための鍵、指導者確保と楽しめる場へ
現状指導者は確保できているものの、教員であるため転勤は避けられない。県内を広く異動する教員と対馬市内を異動する教員がいるというが、それでも継続性に不安が残る。将来的には地元の指導者確保が求められる。
対馬市内には吹奏楽経験者がいることから、藤﨑さんは「活動を継続し、その情報を発信していけば、外部からもアプローチがあるはず。何かしらの活動の場を探している人と、つながる機会はある」と語る。また「子どもたちが続けてくれて、いつか指導者になってくれたらうれしい」と願う。
このプロジェクトは26年2月まで。原田さんは「高いレベルを目指すグループと音楽をもっと気軽に楽しみたいグループを用意し、ニーズに応えられるようにしたい」と抱負を述べた上で「誰でも入っていいんだよ、という雰囲気をつくり、参加すれば自然と楽しめて自然と上達するような場になれば」と語る。
藤﨑さんは「参加して楽しいと思える団体になれば、いずれ送迎支援が必要なくなるかもしれない。例えば今、ダンスが流行っている。ダンスを習いたい子どもたちは、教室が遠くにあっても親が送迎している。最終的には吹奏楽も同じように、親が子どものために送迎する状況に自然になってくれたら」と話した。

=明るい未来に向け活動開始したアンサンブルと指導者、合奏団のメンバー=
投稿者プロフィール
最新の投稿
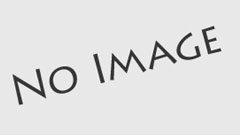 お知らせ2025.12.27年末年始のご案内
お知らせ2025.12.27年末年始のご案内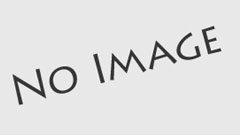 お知らせ2025.11.29【開催案内】休眠預金活用事業2022年度通常枠『こどもの成果発表会』開催!!
お知らせ2025.11.29【開催案内】休眠預金活用事業2022年度通常枠『こどもの成果発表会』開催!!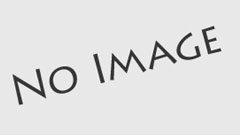 お知らせ2025.05.27【休眠預金】『子どもの移動と体験を考える地域円卓会議in長崎』開催のご案内
お知らせ2025.05.27【休眠預金】『子どもの移動と体験を考える地域円卓会議in長崎』開催のご案内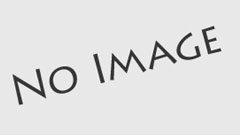 お知らせ2025.04.23【休眠預金】対馬市のユースアンサンブルから広がる音楽の輪(長崎県対馬市 Vol.2)
お知らせ2025.04.23【休眠預金】対馬市のユースアンサンブルから広がる音楽の輪(長崎県対馬市 Vol.2)