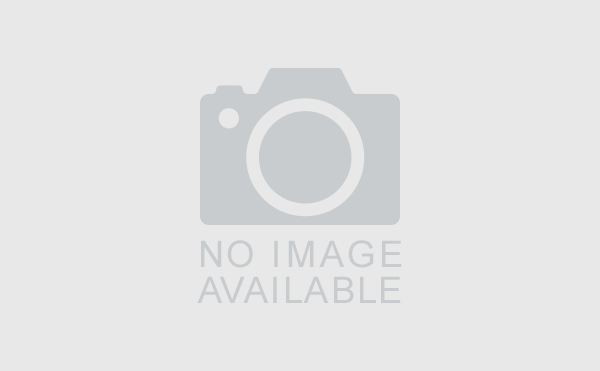【休眠預金】長崎県の一部離島・高島が挑む交通、通信、アートによる未来づくり(長崎県佐世保市 Vol.2)
高島活性化コンベンション協会第2回インタビュー
「数十年後も明るい未来を共有でき、元気な有人島として存続させる」というコンセプトを掲げ、子ども交通難民対策事業や情報インフラハンディキャップ改善事業などの事業に取り組んでいる高島活性化コンベンション協会ESPO。事業をどう展開し、どんな効果を生んだのでしょうか。また、事業を進める中でどんな課題が浮かび上がってきたのでしょうか―。専務理事の重村友介さんに話を伺いました。
子どもの教育機会確保に向けて海上交通を改善
――交通難民対策事業で海上タクシーの増便やダイヤ改正に取り組んだそうですが、そもそもどんな課題があったのでしょうか。
高島には中学校がないため、子どもたちは中学生から海上タクシーで本土への通学を始めます。ただ、便数に限りがあったのに加え、遅い時間帯のダイヤがなかったので、部活動や友達と遊ぶことが制限されていました。実際は部活を諦めるか、あるいは下宿するか、という選択肢しかない状態です。
小学生の習い事の場合でも、親が自分の船で送り迎えをしなくてはいけません。親に仕事がある時は、子どもは習い事を休まなければならず、結局これが常態化していることで「やってみたいけど無理かな」と最初から諦めてしまう、学びの機会を得られずに終わっている子どもたちがいます。
こういう状況を知った時はショックでしたし、何とかしないと、と思いました。教育というのは非常に大切な部分なので、改善されなければ高島という島自体、人が残っていくのは難しいのではないか、とも思いました。
また、多くの島民が、島と本土に1台ずつ車を持っています。家庭によっては、子どものために本土にアパートを借りて暮らしている島民もいます。実際、ESPOメンバーの男性は、自身は漁師で高島に住んでいますが、奥さんとお子さんは相浦にアパートを借りて別々に暮らしている状況です。
――交通難民対策事業ではどんなことに取り組み、どんな効果が生まれつつありますか。
これまでは1日4便の運航でしたが、月水金は夕方の便を1便増やしてもらいました。これによって高校生の登下校の時間に合わせられるようになり、部活動が終わった後でも帰ることができます。塾や習い事も利用しやすくなったと思います。2024年11月から増便とダイヤ改正を実施し、約2カ月しか経っていませんが「ありがたい」という声は多いです。「習い事をやらせてみようかな」とか「子どもに何か新しいことをさせてみようかな」という声も出てきています。親御さんからも喜ばれていると感じています。
運行は海上タクシーの社長さん1人が行っています。増便とダイヤ改正について社長さんに交渉したのですが、70代で1人で運営しているにもかかわらず「全面的に協力させてもらいたい」と快諾していただきました。日が長くなる夏を見据え、4月からは最終便の時間をさらに遅くしてもらう予定です。今後も保護者や社長さんと相談しながら、必要に応じて変更を検討していきたいと考えています。
――持続可能な体制構築に向け、今後どう取り組んでいくつもりですか。
社長さんには当然、休眠預金を活用して経費をお支払いしていますが、休眠預金の事業期間が終了することを見据えて長期的な運営の仕組みを考えなければなりません。船の運転自体は、高島の漁師さんたちも免許を持っているので交代して回すことはできると思います。そうすることで、社長さんの負担は減らせるのではないかと考えています。
運営費の確保については、利用客を増やしていくことを考えています。それには島外から人をどう呼び込むかが大切になると思っています。休眠預金事業を通じて観光客の増加につながる取り組みを進めているので、さらに加速させていければと思っています。また、行政と協力することも考えています。金銭的な協力を得るためには、海上タクシーの必要性をデータや実績で示さなければなりません。今後は、増便やダイヤ改正が子どもたちの学びや保護者の生活にどういう影響を与えたのか、という根拠を集めて佐世保市に相談していくことにも取り組もうと考えています。

=海上タクシーを利用する高島の高校生=
インターネット環境の改善で本土と変わらぬ教育機会を確保
――インターネット環境を改善する事業について、高島の実情や事業に取り組むことになった背景を教えてください。
高島はインターネットがほとんどつながりません。ポケットWi-Fiを持ってきたり増幅器を置いたりしても、回線速度が非常に遅くてほとんど使えません。隣の島や、もっと遠い黒島には光ケーブルが通っているのですが、不思議なことに佐世保市で唯一、高島だけ通っていない状況です。
今の時代、教育面や生活面を考えると最低限のインターネット環境は必須ですが、高島の教育現場ではオンラインで学ぶ機会がなく、本土の子どもたちとの教育格差などの問題が生じていました。そこで光ケーブルの代替手段を探していたところ、スターリンクの存在を知り、導入してみようと思ったのが取り組みにつながっています。
――これまでどんなことを行ったのですか。
スターリンクには個人用と法人用の2種類があります。法人用は数百台の端末を同時接続できるので、法人用を相浦小学校の分校にある多目的トイレの屋根に設置する予定です。これに向けて2024年夏ごろから、個人用の端末を様々な場所に設置し、通信速度などを確認しました。天候が悪い時の状況も確認しました。
インターネットは問題なくつながりました。本土で暮らしていると、つながるのが当たり前で、スマホで動画を観るのも普通のことだと思います。でも、それが当たり前ではなかったんです。だから、試験的に利用した子どもから60代までの島民は「動画が止まらない」「音声も途切れない」、「すごい」と喜んでいました。もちろん、私も感動しました。
教育現場でも試験利用してもらいました。これまではタブレットを使ったオンライン学習が十分できなかったり会議中に映像が止まってしまったりしていたそうですが「こんなにスムーズにつながるのは初めて」という声が多く、皆さん感激していました。
――今後の展望を教えてください。
スターリンクの利用には当然、利用料が発生します。休眠預金事業が終わったから払えない、ということにならないようにしなければなりません。通信環境は今の時代、ガスや電気などと同じくらい重要なインフラなので、休眠預金事業を始める前から行政には支援を求めてきました。
海底ケーブルを引くには7、8億円かかることが見込まれているため、非常に難しい問題です。しかし、デジタル田園都市国家構想の交付金などの制度を活用していくのか、話し合いを進めていますし、空白期間が生まれないように今後も議論を尽くしていきたいと考えています。

=スターリンクの通信速度を確認するESPOメンバー=
地域の誇りを育むアートプロジェクト
――アート事業を通して地域への誇りを醸成する取り組みも進んでいますね。
老朽化で捨てられる予定だったバス停のベンチを13台ほど高島に持ち込み、昨年の11月30日に高校生までの子どもたちと一緒にベンチに絵を描きました。完成後は島の各所に置いたのですが、お年寄りも子どもも利用できる「ちょっと休める場所」になっています。彩りがあるから雰囲気も明るくなりました。「インスタにアップしよう」なんて話も聞きます。「やって良かった」という声をたくさんいただいています。
来年度以降は、岸壁アートに取り組む予定です。アート事業の一環で韓国の影島(ヨンド)などを視察したのですが「スラム街だったエリアをアーティストたちと一緒に少しずつアートで盛り上げてきた」という話を聞き、高島でもそういう視点を忘れずに次の展開につなげていけたらと思っています。

=子どもと大人が協力して島を彩るベンチを完成させた=
投稿者プロフィール
最新の投稿
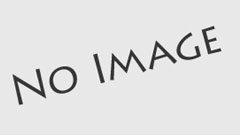 お知らせ2025.12.27年末年始のご案内
お知らせ2025.12.27年末年始のご案内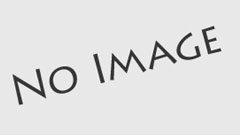 お知らせ2025.11.29【開催案内】休眠預金活用事業2022年度通常枠『こどもの成果発表会』開催!!
お知らせ2025.11.29【開催案内】休眠預金活用事業2022年度通常枠『こどもの成果発表会』開催!!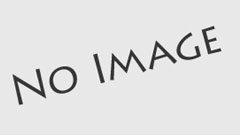 お知らせ2025.05.27【休眠預金】『子どもの移動と体験を考える地域円卓会議in長崎』開催のご案内
お知らせ2025.05.27【休眠預金】『子どもの移動と体験を考える地域円卓会議in長崎』開催のご案内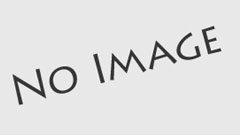 お知らせ2025.04.23【休眠預金】対馬市のユースアンサンブルから広がる音楽の輪(長崎県対馬市 Vol.2)
お知らせ2025.04.23【休眠預金】対馬市のユースアンサンブルから広がる音楽の輪(長崎県対馬市 Vol.2)